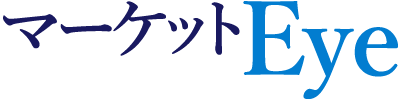【知っておきたい為替と株価の関係性】今日の相場解説 (2025.01.15)デイリーマーケットレビュー
【知っておきたい為替と株価の関係性】今日の相場解説 (2025.01.15)デイリーマーケットレビュー
最終更新日: 2025-01-15
ページ制作日: 2025-01-15
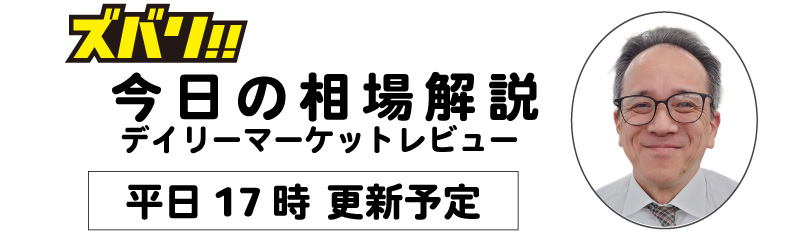
成人式は何日?
昭和時代を過ごした私たちにとって、成人式といえば「1月15日」と頭にインプットされている方が多いかと思います。 しかし現在では、成人式はこの日に固定されていません。では、いつから1月15日ではなくなったのかというと、平成12年(2000年)から「1月の第2月曜日」に変更されました。この背景には、ハッピーマンデー制度の導入があります。
ハッピーマンデー制度の目的
この制度は、観光業や運輸業などを活性化させることを目的として導入されました。祝日と週休2日制をつなげることで3連休以上の期間を増やし、国民が旅行やレジャーを楽しみやすくするため、いくつかの祝日が従来の日付から特定の月曜日に変更されました。ハッピーマンデー制度によって変更された主な祝日は以下の通りです。
- 成人の日:1月15日 → 1月第2月曜日
- 体育の日(現:スポーツの日):10月10日 → 10月第2月曜日
- 海の日:7月20日 → 7月第3月曜日
- 敬老の日:9月15日 → 9月第3月曜日
現在の成人年齢について
また、成人年齢に関する法律も大きく変わっています。2022年4月の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この改正に伴い、成人式の対象年齢や自治体の運用方法にも変化が見られています。 いかがでしょうか?時代とともに変化してきたこれらの制度や法律。振り返ることで、その背景にある目的や社会の流れが見えてきますね。
今日の解説は「株価」です。
本日は、年明け以降取り上げていなかった日経平均株価について解説します。
今年は巳年であり、株や相場の世界でよく知られる干支にまつわる相場格言「辰巳天井」の年に該当します。
巳年に関する詳しい内容については、昨年12月30日に掲載した記事もぜひご参照ください。
日経平均株価(日足)
.jpg)
2024年の動きを振り返ると、あのバブル時代の高値を超え、日経平均が4万円台に突入したのが3月でした。
その後、調整を挟みながらも最高値を記録したのは7月。しかし、8月にかけては急激な下落が発生し、その動きは非常に強烈でした。この期間、ドル円も大幅な円高に振れていたのが特徴的です。
ドル円(日足)
.jpg)
特に昨年8月5日の日経平均株価は、3万5000円台前半で始まった後、午後には3万1000円台前半まで一気に下落しました。終値は前営業日比で「4451円安」となり、下げ幅は1987年の米ブラックマンデー翌日を上回る過去最大を記録しました。
さらに、「下落率12%」という数字は歴代2位の大きさでした。
一方、ドル円相場は年初来ほぼ一貫して円安が進行し、7月3日には1ドル=161.94円に到達しました。しかし、そこから相場は反転し、ドル安円高が進行。7月31日には150円だったドル円が、8月5日までの間に一時141円台を付けるほど急速に円高が進みました。
この期間、株価の暴落とドルの暴落(円の急騰)が同時進行していたことが特徴的でした。
なお、ドル円は9月16日に140円割れを記録しましたが、株価も同様に下げ続ける一方、8月5日のインパクトが大きすぎたため、最安値には至らず35,247円で踏みとどまりました。8月5日の安値には4,000円の余裕があったことになります。
現在では「円安=株高」という傾向が一般的ですが、2000年代初頭までは為替レートと株価の関係は必ずしもそうではありませんでした。特に1980年代後半は「株高、土地高、円高のトリプルメリット」という言葉が広く使われており、これが当時の経済成長を支えた要因とされています。当時は「バブル景気」と呼ばれる1980年代後半の経済を、三高景気という表現で捉えていた時代です。特に60代の方には、こうした記憶が鮮明に残っているのではないでしょうか。
為替レートと株価の関係の変化について
ここまで為替レートの影響が大きく変化した背景には、いくつかの要因が挙げられます。
- 上場企業の構造変化 まず、上場企業の構造そのものが変わったことが影響しています。TOPIXは時価総額加重平均で算出されるため、大企業の影響が特に大きいのが特徴です。 1980年代後半、TOPIXの上位にはNTT、大手銀行、電力会社などの内需系企業が圧倒的に多く、円安はむしろ指数にとってマイナスでした。当時は、自動車などの大手輸出企業も現在ほどの影響力はなく、日経平均株価でも同様の相関が見られていました。
- 日本企業による海外資産の買収 次に、当時の日本企業は円高を利用した海外資産の積極的な買収が進んでいました。例えば、ソニーによる米コロンビア・ピクチャーズの買収や、三菱地所によるロックフェラーセンターの買収など、いわゆる「ジャパンマネーの席巻」が期待されていた時代です。これらの動きは企業価値の向上や株価の押し上げに寄与しました。特にロックフェラーセンターの買収は、アメリカの象徴を手に入れたとして大きな話題となり、現在で言えばUSSスチールを買収するようなインパクトがありました。
- 円高と利下げ観測の関係 当時は、円高が進行すると利下げ観測が高まりやすい傾向がありました。この利下げ期待が景気回復への期待感を高め、結果的に株高を招く要因となっていました。
社会構造の変化と新たな投資スタンス
昨年、日経平均がバブル時代の高値を更新したのは、1980年代後半とは大きく異なる社会構造や産業構造の中での出来事でした。当時は「株式は長期保有で持てば良い」と言われる時代もありましたが、現在では主要産業の変化やかつての主力業種の斜陽化が進んでいます。 こうした中で、株式投資に対する考え方も大きく変える必要があります。社会や産業が変化する中で、かつての成功モデルに固執することなく、柔軟に投資のスタンスを見直すことが求められる時代となっているのです。
なぜ円安になると株が買われるのか?
円安が進むと、日本の株式市場が海外投資家にとって「割安」に見えるためです。海外投資家が株を買う流れを具体的に説明します。
- 海外投資家のポートフォリオのルール 海外投資家は、日本株を一定の割合で保有するという投資ルール(ポートフォリオ)を組んでいます。この割合は、国や地域ごとに決められており、日本株もその中に含まれています。
- 円安が進むとどうなるか? 円安になると、ドルなどの外国通貨で見た場合の日本株の価値が下がります(例:同じ株でも円安でドル建ての価格は安くなる)。その結果、ポートフォリオ内で日本株の割合が下がり、ポートフォリオのルールからずれてしまいます。
- 割合を元に戻すために株を購入 ポートフォリオのバランスを保つために、海外投資家は日本株を買い増します。この動きが、円安時に日本株が買われる理由の一つです。
円建て日経平均株価(月足)
.jpg)
ドル建て日経平均株価(月足)
.jpg)
日経平均株価を「円建て」で見るのと「ドル建て」で見るのでは、その印象が大きく異なります。
日本の株式市場は、売買の約6~7割を外国人投資家が占めており、彼らにとっては基軸通貨である米ドルで見た株価が重要な指標となっています。そのため、為替の変動が日本株の売買に直接影響を与える仕組みになっています。
円安になると、ドルで見た場合の日本株の価値が下がります。例えば、円安が進んで1ドル=100円から120円になると、ドル換算で日本株は割安に見えるようになります。
すると、外国人投資家のポートフォリオにおける日本株の割合が低下します。この割合を基準値に戻すために、彼らは日本株を買い増しする傾向があります。
一方で、円高になると、ドルで見た日本株の価値が上がり、ポートフォリオ内の日本株の割合が高まります。基準値を超えた割合を調整するために、外国人投資家は日本株を売却する傾向が強くなります。
このように、円安は日本株の買い材料に、円高は売り材料になるケースが多いのです。
日本株市場においては、外国人投資家の存在感が大きく、為替レートが株価に与える影響も非常に重要です。円建てとドル建てのチャートを比較してみると、こうした影響が一目でわかるため、投資判断に役立つ視点の一つと言えるでしょう。
今日の相場解説
少し材料面の話が多くなってしまいましたがチャート面でのチェックをしたいと思います。
日経平均株価(日足)
.jpg)
年末に日経平均株価は40,398円まで上昇し、10月以降囁かれていた「4万円上値上限説」を打破するかと期待されました。しかし、その期待に反して株価は引き続きレンジ相場(38,000円~40,000円)の中にとどまっています。
2025年に入り、短期・中期・長期の移動平均線(MA)をすべて下回る動きに変わり、現在ではレンジ下限の38,000円に接近しています。
このまま1年間、38,000円~40,000円のボックス相場が続けば、逆張り戦略で利益を狙うことも可能ですが、市場はそう簡単には動いてくれないでしょう。
特に年末にレンジ上限を抜けた局面では、「2025年に向けて好スタート」と見て買い向かった投資家も多かったはずです。
「3カ月続いた停滞相場(レンジ相場)ともこれでお別れ」と市場が盛り上がる中、結果としてその期待は裏切られ、再びレンジ内に戻る形となりました。
現在の焦点は、レンジ下限の38,000円を割り込むか否かです。この水準を買い目線で捉えた投資家にとっては、全力で守るべき重要なラインとなっています。
また、この価格位置では、為替に関連する大きなイベントが控えており、2025年全体の方向性を占う意味でも非常に重要な局面を迎えています。
さらに、今年はトランプ政権の再始動により、彼の発言が株価を乱高下させる可能性も高く、昨年以上にマーケットの動きに注意が必要です。今後の展開において、38,000円の死守が鍵となり、為替や国際的な政治動向が株価に与える影響をしっかり注視することが重要です。
セミナーのご案内
東京、福岡、沖縄で投資セミナーを開催いたします。直接、相場についてお話させていただきますのでお気軽にお申込みください。
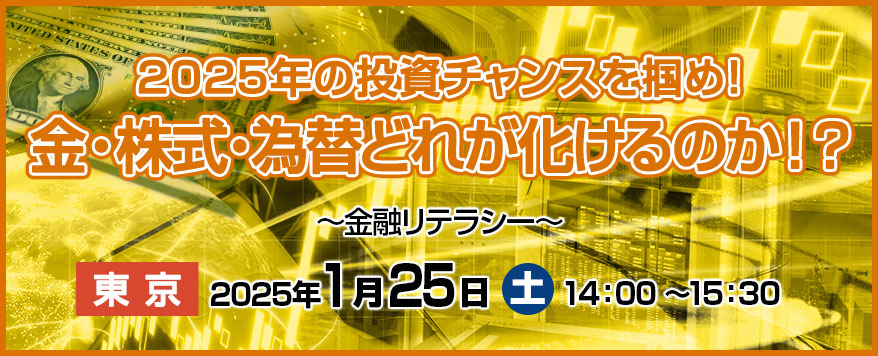
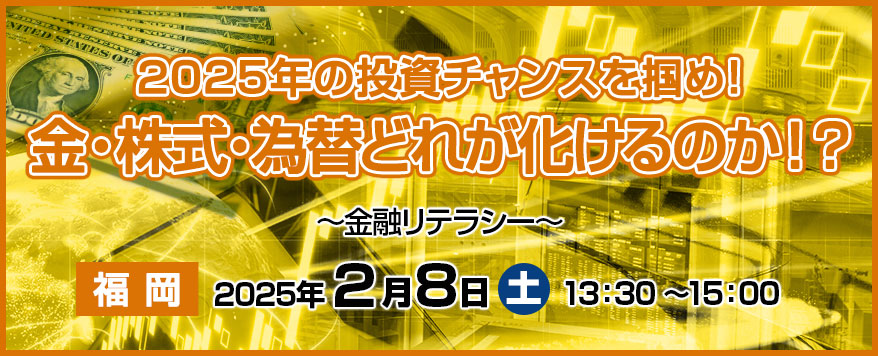
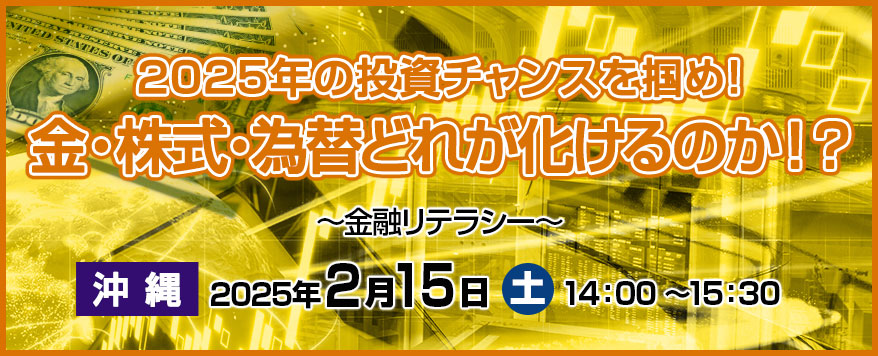
情報サイト「マーケットEye」は、当社のお客様向けに投資に役立つ情報を提供するサイトですが、一般の投資家の皆様にもお楽しみいただけるオープンコンテンツもご用意しています。
さらに、2週間の体験キャンペーンでは全てのコンテンツをご覧いただけますので、お気軽にお申し込みください。
この記事が役立ったらシェアをお願いします!
Tweet※tradingview社のチャートを利用しています。
- ご注意ください。
-
当サイトの情報は各アナリストがテクニカル分析に基づき作成したもので、相場の動向を保証するものではありません。
売買に際しての最終判断はあくまでもご自身でご決定ください。 商品関連市場デリバティブ取引及び商品先物取引は元本や利益が保証されるものではなく、 価格の変動により場合によっては委託証拠金の額を上回る損失が生じることもあります。 為替、日経平均株価の分析は、商品市場分析の参考データとしてご提供しております。 当社では、外国為替証拠金取引及び日経平均指数先物取引の取り扱いはしておりません。
なお、予告なしに内容が変更又は、廃止される場合がありますのであらかじめご了承ください。
お取引の際は事前に 重要開示事項 等を十分ご理解のうえ、ご自身の判断で行なって頂けますようお願い申し上げます。